不要な郵便物は受け取り拒否が可能!|拒否の方法や注意点を解説
 2024年9月13日
2024年9月13日
 その他
その他
 全国
全国
 214
214
「不要な郵便物が届くので受け取り拒否したい」
「差出人不明のゆうパックを受け取るのが怖い」
「前の住人の郵便物が届いて困っている」
このような悩みを抱いている方は、実は多いのではないでしょうか。
日々さまざまな郵便物が届きますが、時には迷惑な郵便物や差出人の書かれていない郵便物など、受け取りたくないものもあるでしょう。「届いたからには受け取らなければ」と考える方もいるかもしれませんが、郵便物には「受取拒否」という選択肢もあるのです。
本記事では、不要な郵便物や迷惑な郵便物を受取拒否する方法について解説します。拒否できる郵便物の種類や注意点も解説するので、郵便物に悩んでいる方はぜひご一読ください。
不要な郵便物は受け取り拒否が可能

法律上、自宅に届いた郵便物の受け取り義務はありません。受け取るかどうかは本人の意思に任されているため、不要な郵便物は受取拒否しても問題ないのです。
たとえば以下のような郵便物は、「不要」「受け取りたくない」と感じる方も多いと思います。
- しつこいダイレクトメールやパンフレット
- 差出人が分からない郵便物
- いたずら目的や詐欺目的の郵便物
もちろんこうした郵便物は、自宅で開封したうえで処分しても構いません。郵便物を開封しないと要・不要の判断ができないこともあるでしょう。
一方、一目で不要と分かる郵便物には「そもそも受け取らない」という選択肢も存在します。それを知っておくと、いざという時に役立つと思います。
受け取りを拒否できる郵便はさまざま
自宅に届く郵便物には、さまざまな種類があります。そして手紙はもちろん、以下のようなサービスも受取拒否することが可能です。
- はがき
- ゆうパック、ゆうパケット
- レターパック
- クリックポスト
ただしネットショッピングなどで事前に商品の料金を支払った場合は、受取拒否してもその分が返金されるとは限りません。ネットショップによってはキャンセル期間が設けられているので、事前に確認しておきましょう。
不要な郵便物を受け取らず返送する方法
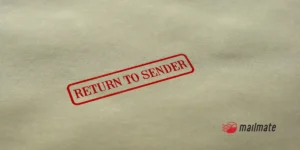
ここでは、上述した不要な郵便物等を受け取らずに、返送する方法をご紹介します。手順はシンプルですし、一切料金はかかりません。知識さえあれば、すぐに実践することができますよ。
またマンションやアパートに住んでいると、前の住人に宛てた郵便物が届くこともあるかもしれません。勝手に開封や処分ができず、困ることもあるでしょう。そんな時の対処法についても、あわせて解説します。
手順1)メモや付せんに「受取拒絶」と書く
まずはメモや付せんを用意し、「受取拒絶」と記載します。メモや付せんがはがれないよう、上からテープなどで留めておくと安心ですね。どうしてもメモや付せんが用意できなければ、封筒に直接書くこともできます。あわせて受取拒否した本人の押印、またはフルネームの署名を残してください。
例外は、特別あて所配達郵便物です。これは住所の記載さえあれば、受取人の名前がなくても配達される郵便物のこと。この場合は押印や署名が不要となるので、「受取拒絶」の文字だけを記せば問題ありません。
手順2)郵便窓口へ持参するかポストに投函する
郵便物にメモや付せんを貼ったら、郵便窓口へ持参しましょう。あるいは一般書留郵便物などの直接配達員から渡される郵便物であれば、その場で配達員に返しても問題ありません。
郵便窓口へ持参するのが手間だという方は、街中の郵便ポストに投函することもできます。特に切手などを貼りなおす必要もなく、メモや付せんを貼ったまま投函するだけで大丈夫です。郵便窓口の場合は営業時間が限られるため、忙しい方にはポスト投函が便利かもしれませんね。
【参考】前の住人の郵便物が届いた場合
マンションやアパートに引っ越したばかりだと、前の住人の郵便物が届くこともあるかもしれません。私も見知らぬ人宛の郵便物がポストに入っており、驚いた経験があります。
たとえ自分のポストに入っていた郵便物でも、第三者に宛てた郵便物の開封や破棄はできません。郵便法第42条では、このような誤配達について定められています。
誤配達の対応も、受取拒否の手順とほぼ同じです。郵便物の表面にメモや付せんを貼り、郵便窓口へ持参、または郵便ポストに投函しましょう。メモや付せんには「転居先不明」「前の居住者である」等と記し、事実を簡潔に伝えてください。
誤配達があった旨を、郵便局やお客様相談センターに連絡する方法もあります。
郵便物を受け取り拒否する際の注意点

郵便物の受け取りを拒否する方法はシンプルですが、対応を誤ると拒否ができなくなってしまいます。ここでは主な注意点を3点解説するので、しっかり確認しておいてください。
郵便物を開封してはいけない
受取拒否できる郵便物は、未開封のものに限ります。少しでも開封してしまうと、配達が完了したことになり、返送することはできません。
なかでも注意すべきは、書留やゆうパックのように受領のサインや押印が必要な郵便物です。この場合は、サインあるいは押印した時点で受け取ったことになってしまいます。そのため受け取り時に差出人を確認し、違和感があったらその時点で受取拒否をしてください。
例外として、マンションの管理人等が受け取った際は、受領してから時間が経っておらず未開封の場合に限って受取拒否が可能です。ただし配達証明や代金引換を利用していないことが条件で、利用していた場合は受取拒否ができなくなってしまいます。
参考:受領印を押してゆうパックを受け取ったが、やはり受取拒否をしたい – 日本郵便
本人以外は受取拒否ができない
たとえば書留郵便の場合、本人不在時には同居家族が受け取ることも可能です。その際に「この差出人からは受け取らない方が良い」と気付くこともあるでしょう。
だからといって、本人以外が郵便物の受取拒否をすることはできません。本人が受取拒否をする可能性があるなら、その場では不在扱いにしておくと良いですね。そのうえで、本人が在宅している時間に再配達してもらいましょう。再配達時に本人が受取拒否をするのであれば、特に問題ありません。
上述のとおり一度受領のサインをすると、その後の受取拒否はできなくなるので注意が必要です。
日本郵便以外の配達物は配送業者に連絡が必要
一見通常の郵便物であっても、表面に「これは郵便物ではありません」「〇〇メール便」などと記載されているものは、日本郵便が配達した郵便物ではありません。間違えやすいものに、以下のサービスがあります。
- クロネコヤマトの「クロネコDM便」
- クロネコヤマトの「ネコポス」
- 佐川急便の「飛脚メール便」
Amazonなどのネットショップで注文した商品には、こうしたサービスが使われていることも多いです。
このように日本郵便以外が配送した荷物は、上述の方法での受取拒否ができません。荷物の表面に連絡先が載っていることもあるので、確認したうえでそれぞれの配送業者に連絡しましょう。
郵便物を受け取り拒否したらどうなる?

受け取りを拒否した郵便物はいったん郵便局に戻されますが、その後の流れは差出人が分かっているかどうかで変わってきます。ここではそれぞれの流れを確認していきます。
また一般郵便物と違って、内容証明郵便や特別送達には少し注意が必要です。受取拒否することも不可能ではありませんが、受取拒否した場合は自分にもデメリットが生じるかもしれません。詳しく見ていきましょう。
差出人が分かっている場合
差出人が分かっているのであれば、郵便物は差出人に返送されます。差出人がその郵便物を破棄すれば、それで終わりとなります。
この時「受取拒否したことを相手方に知られたくない」という方もいるかもしれませんが、残念ながらそれは不可能です。郵便局員がメモや付せんを剥がすことはないので、受取人が封筒に貼り付けたメモや付せんは、そのままの状態で差出人に返送されます。そのため差出人は、受取人に拒否されたことが分かるのです。
そのため差出人と直接連絡が取れるのであれば、受取拒否した理由などを伝えると良いかもしれませんね。
差出人不明の場合
差出人不明の郵便物は、郵便局で一度開封したうえで中身を確認します。そこで差出人が判明すれば、差出人へと返送されます。「あれは誰から届いた郵便物だったのだろう」と気になる方もいるかもしれませんが、特に郵便局から連絡がくることはありません。
一方で差出人が分からないままの郵便物は、しばらく郵便局で保管されます。保管期間は3カ月間で、この間に差出人が現れなければ、郵便局で破棄されることとなります。
内容証明郵便は受取拒否しても届いたとして扱われる可能性がある
内容証明郵便とは、日本郵便が以下の点について公的に証明してくれる郵便のことです。
- いつ送付したか
- 誰が送付したか
- 誰に送付したか
- どんな内容を送付したか
内容証明郵便には法的効力があり、裁判時の証拠としても有効です。そのため離婚の話し合い、クーリングオフなどの場面で多く使われます。
内容証明郵便を受取拒否した場合、郵便局での保管期間は7日間です。その後「受取拒否」「不在」等の理由を添えて、差出人へ返送されます。
ただし本人が受け取れる状態であり、かつ内容に推測が付いていたのに受け取らなかった場合、実際に受け取らなくても「届いた」として扱われることがあります。「知らなかった」では済まないので注意しましょう。
特別送達を受取拒否すると自分が不利になる
日常生活で受け取る機会はほとんどありませんが、もしも特別送達が届いた際には、必ず受け取ることをおすすめします。特別送達とは、裁判所や特許庁などの公的機関から送られてくる重要な郵便物のこと。ポストに投函されるのではなく、配達員から直接受け取ります。
この特別送達に対しては、受取拒否はできません。それは同居家族や同僚が受け取ることも可能なうえ、配達員がその場に置いていった場合でも送達完了とみなされるため。もし本人が受け取らなかったとしても、効力を発揮する郵便物なのです。
また特別送達を受取拒否した場合、裁判において不利になります。特別送達が届いたなら、必ず受け取って中身を確認しましょう。
送った郵便物が返送されてきたらどうする?

反対に自分の送った郵便物が受取拒否され、返送されてくる可能性もあります。受取拒否はあくまでも「受け取りたくない」という意思を示したもので、「今後送ってはいけない」という意味ではありません。そのため必要であれば、郵便物を再送することは可能です。
とはいえ一度受け取りを拒否されたのであれば、繰り返し送ることはおすすめできません。特にダイレクトメールなどの場合は「不要」と判断されたのであり、何度も送ることで「しつこい」という悪印象につながる恐れがあります。
ただ、相手方の受取拒否ではなく、住所や宛名の書き間違いによって返送される場合もあります。その際は正しい情報に書き直し、改めて郵送するのも良いですね。
商品の購入者に受取拒否された場合
レアなケースではありますが、なかにはメルカリなどネットショップで発送した荷物が、購入者によって受取拒否される場合もあります。送料などは発送元の負担となるので、リスクが大きいですね。
このような場合は運営事務局が間に入ってくれることもありますが、当事者間でのやり取りが基本です。だからこそトラブルを未然に防ぐことが重要となります。
購入者による受取拒否を防ぐためにも、出品の際は以下の点に注意しましょう。
- キャンセル期間を明記しておく
- 発送後にキャンセルした場合にかかる料金の扱いを定めておく
たとえば「キャンセル期間は注文後24時間以内」「発送後にキャンセルした際の送料は購入者負担」等の記載があると安心です。
不要な郵便物の返却方法を知っておこう

本記事では不要な郵便物に悩んでいる方に向け、郵便物を受け取り拒否する方法について解説しました。ただし日本郵便が配達した郵便物に限った方法なので、その他の荷物については各配送業者に確認してください。
未開封であれば封書やはがきだけでなく、ゆうパックやレターパックなども受取拒否することが可能です。メモや付せんを貼りつけて郵便窓口へ持参、あるいはポストへ投函するだけなので、手続きも簡単です。
自宅で郵便物を処分する場合、その後も繰り返し送られてくる可能性があります。「受け取りたくない」という意思を示すことで、以降の送付も止められるかもしれません。そのためにも「受取拒否」という選択肢を知っておくと良いですね。
メールメイトなら郵便物の管理がしやすい
今回は不要な郵便物について取り上げましたが、なかには「そもそも郵便物の管理が大変」という方もいるでしょう。要・不要問わず、未開封の郵便物が溜まってしまう方も珍しくありません。
そんな方には、電子メールと同じように郵便物の管理ができる、クラウド私書箱がおすすめです。メールメイトなら郵便物をPDFデータとして受け取れるうえ、簡単操作で自宅への転送や破棄も可能。郵便物の検索や共有もしやすく、スムーズに郵便物管理ができます。
また「自宅住所を知られたくない」「ストーカー被害が怖い」という方にも、私書箱サービスはおすすめです。30日間は無料で試用できるので、気になる方はぜひメールメイトに登録してみましょう。


 MailMate
MailMate